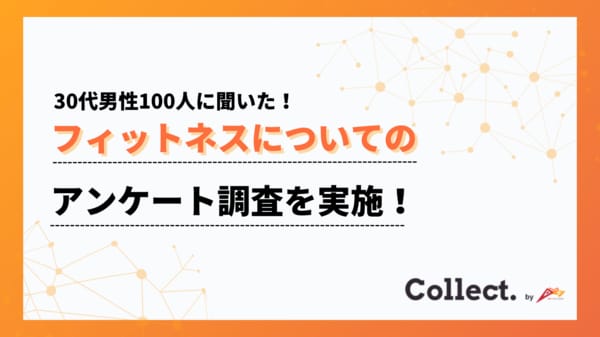「飲酒は当たり前?」から「健康第一」へ。無理な禁酒ではなく、自分に合った付き合い方を見つける社会へ
2025-06-17

プレジデントオンライン
「飲酒は当たり前」という固定観念から脱却し、健康を最優先する社会へ
長年、日本では「お酒は社交の場に必須」という考え方が根強く、飲酒が当たり前のように扱われる場面も少なくありませんでした。しかし、健康意識の高まりとともに、「無理に飲まなければならない?」という疑問の声も上がっています。重要なのは、教条主義的な完全な禁酒を求めるのではなく、一人ひとりが十分な情報に基づいて、自分にとって最適なアルコールとの距離感を見つけられる社会環境を整備することです。
なぜ今、アルコールとの付き方を考える必要があるのか?
アルコールの過剰摂取は、肝臓疾患や生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、依存症や家庭内暴力などの深刻な問題を引き起こす可能性もあります。また、社会全体で見ても、アルコール関連の医療費や労働生産性の低下など、経済的な負担も無視できません。
無理な禁酒は逆効果?
アルコールを完全に断つことが必ずしも良いとは限りません。無理な禁酒は、ストレスや孤独感を増幅させ、かえって健康を害する可能性もあります。大切なのは、自分の体質やライフスタイルに合わせて、適度な飲酒を楽しむか、控えるかを判断することです。
理想の社会とは?
私たちは、一人ひとりがアルコールに関する正しい知識を持ち、自分の健康状態や価値観に基づいて、自由に選択できる社会を目指すべきです。そのためには、以下の取り組みが重要になります。
- 正確な情報提供: アルコールの健康影響に関する科学的な情報を、わかりやすく提供する必要があります。
- 飲酒に関する教育: 子供の頃から、アルコールに関する正しい知識を身につけるための教育が必要です。
- 飲酒習慣の見直し: 職場や家庭内で、無理な飲酒を強要しない雰囲気づくりが求められます。
- 多様な選択肢の提供: アルコールを飲まない人でも楽しめるイベントや交流の場を増やすことが重要です。
未来へ向けて
「飲酒が当然視される社会」から「健康が重視される社会」への転換は、決して簡単な道のりではありません。しかし、一人ひとりが意識を変え、社会全体で取り組むことで、より健康的で豊かな社会を実現できると信じています。
アルコールとの付き合い方を見直すことは、自分自身だけでなく、家族、職場、そして社会全体にポジティブな影響をもたらす選択となるでしょう。今日から、自分にとって最善のアルコールとの距離感を考えてみませんか?